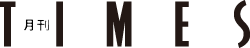政治•経済
選挙の主役となるシルバー世代からの批判を恐れず生産世代を意識した政策 先に行われた衆議院選挙において大方の予想通り自公政権の議席が過半数を割り込む与 党にとっては厳しい結果に終わった。自民党安倍派の政治資金パーティーの収益のキック バックを収支報告書に記載していなかった不記載問題への岸田政権の対応は生ぬるく国民 の反感は思った以上に大きかったということだろう。自民党総裁選挙が終わり石破新総理 が選ばれて首脳部を刷新し新政権が誕生したばかりの時期にはご祝儀的に支持率が一定期 間支持率が上振れる。その期間を狙い撃ちした解散総選挙であったが、自民党が思ってい たほど国民の歓迎機運は続かない。総選挙が公示されると石破政権の支持率は徐々に下落 。選挙戦半ばには多くのメディアで与党の過半数割れの可能性が報じられるようになる。 新政権は瞬く間に新鮮味を失い旧態依然としたように映る中、自民党の選挙戦略も良くな った。「ルールを守る」というキャッチフレーズを展開したのだ。このキャッチフレーズ を聞いたり目にした多くの国民は「あたりまえだろ」とか「小学生か」と突っ込んでいた ことだろう。冗談のようなキャッチフレーズの下で自民党の支持率は急降下。テレビなど のメディアでは不記載を犯した下村博文氏や羽生田光一氏、三林裕巳氏など大物議員たち が苦戦を強いられる様が面白おかしく報道される。和歌山では5年で50億円もの政策活動 費を使ったと言われる二階俊博氏の後継の三男と不記載問題で除名された世耕弘成氏との 壮絶な選挙戦が注目された。メディアはまるで悪対悪の頓珍漢な戦いをコントの如く演出 し選挙戦を煽る。終盤に差し掛かると自民党から非公認とされた議員に公示後にも関わら ず2000万円が党本部から支給されたことが公になる。非公認なのに党勢拡大を目的とする 政治活動費を振り込む意味がわからない。党とは関係なく戦うことを強いられた候補に党 勢拡大活動の費用を渡してどうするものか。共産党赤旗にスクープされたこの問題も自民 党大敗の大きな要因になったことは間違いない。 事業者ではなく政治家に問題を見出す こうした自民党の転落劇の裏で急速に支持を拡大した政党がある。玉木雄一郎氏が率い る国民民主党である。国民民主党と言えば旧民主党の残党と小池百合子氏が創設し総選挙 で惨敗した希望の党で辛うじて生き残った議員らで結成し、さらに数年後には所属議員の 半数以上が立憲民主党に移ってしまうという事態に見舞われたオワコン政党の印象しかな い。世間では連合(日本労働組合総連合会)の組織内議員が既得権益として生き残った集 まりと思われていた。概ねその通りで国民民主党の議員の多くが労組の組織内議員と言っ ていい。自動車総連、UAゼンセン、電機連合、電力総連などは国民民主党に組織内議員を 有する。つまり、国民民主党は労働者向けの政策を前面に押し出してきた政党と言える。 春闘を年中やっているようなイメージの賃上げ要求政党であった。ただ近年の春闘を思い 起こすと多くの業界で3年以上の満額回答を獲得している。コロナ禍であっても満額の回 答を得ている。多くの大企業で賃上げ率は5%程度に膨らんでいる。歴史的高水準の賃上 げを獲得している一方で国民の生活水準には変化が見られない。変化がないどころか実質 賃金は何故か低下し続けている。給料は上がっているのに手取りは減り続けている。この 現象を踏まえてやっとというか今更というか漸く問題の本質に気が付いたのが国民民主党 であった。大企業から中小企業まで事業者は人材確保の観点から歯を食いしばって賃上げ に取り組んできた。一方、政治家や財務省は労働者の上がった賃金を消費税増税や健康保 険料や年金の負担増で刈り取ってしまっている。エネルギー料金の高騰、輸入物価の高騰 がそこへ追い打ちをかける。日銀の追加利上げというデフレ政策まで登場する始末。賃上 げが物価上昇に追いつかない所謂スタグフレーションの状態に陥っている。国民民主党は その活動方針を「給料を上げる」から「手取りを増やす」に大きく転換した。「事業者に 頼る」政策から「政治による税制改革と経済政策」へと施策を移行することで連合の一機 関的既得権益政党から脱皮する切欠を得た。連合にしか響かなかった政策が広く国民に支 持されるようになったのは国民民主党の立ち位置が大きく変わったからに他ならない。 例えば、所得税法についてはこうだ。現在の所得に対する基礎控除を103万円から178万 円まで引き上げるというもの。学生アルバイトやパートだけに恩恵のある政策ではない。 控除額が75万円分拡大し、全ての働く人の課税対象所得が減ることで大きな減税効果が及 ぶ。年収200万円の人は8.6万円の減税。年収300万円の人は11.3万円の減税、年収500万円 の人は13.2万円の減税、年収600万円の人は15.2万円の減税、年収800万円以上の人は22.8 万円の減税となる。これらの全税額はおおよそ消費税を5%に引き下げた時と同程度とな る。基礎控除を178万円まで引き上げる根拠はこの30年間の最低賃金の推移にある。現在 の基礎控除103万円は1995年から約30年間変わっていない。一方、最低賃金は1.73倍上が っている。30年間を経過した賃金上昇率に合わせて基礎控除額を上昇させると178万円に なる。東京の最低賃金は10月から1163円に引き上げられた。石破総理は2030年までの全 国の最低賃金を1500円にする意向を表明している。もし、基礎控除が103万円のままだと パートやアルバイトをしている人材は極限まで枯渇する。103万円を超えると扶養控除や 健康保険の扶養家族から外れることになる。学生アルバイトや共働きのパートは基礎控除 額の範囲内で働いている者が圧倒的に多い。このまま最低賃金ばかりが上昇すると労働力 不足は更に深刻となり経済成長を阻害する。国民民主党の打ち出す基礎控除を178万円ま で引き上げるという政策は控除による減税効果だけでなくパート、アルバイト等の労働力 の供給を後押しするという効果も備えている。また、控除の引き上げによる所得の圧縮に より健康保険料や年金も減額される効果が見込める。また、年金受給者にとってもメリッ トはある。年金の増額率は賃金や物価によって決まる。2024年は2.7%が増額された。所 謂「103万円壁」が178万円まで引き上げられることで多くの者が気兼ねなく現在よりもた くさん勤務することができるようになる。つまり、全体的に収入は一定程度上昇すること が予想できる。それに引かれて年金受給額もスライドすることになる。 三方よしのハイブリッド政策 国民民主党が唐突に打ち出した「103万円の壁」の打破、基礎控除の引き上げは、実質 的に所得税減税となり労働者にとっての利益となり、労働力の増加に繋がることから事業 者の後押しにもなる。そして、生産世代の収入の上昇と経済発展による物価上昇は年金受 給額の上昇にもつながる。労働者よし、事業者より、シルバー世代よし、の3方よしを叶 えるハイブリッド政策なのだ。 ところで、このような耳障りの良い政策を実行するための財源はどうするのかという疑 問を多くも者が持つだろう。現状において財源は心配に及ばない。政府税収は3年連続過 去最高を記録している。政府には18兆円近くも基金が積みあがっている。それ以外にも為 替差益が20兆円以上発生している。政府短期証券を発行することで外貨準備を崩さずに含 み益を一般会計に繰り入れることが可能だ。要するに政府には十分すぎる財源がある。消 費税減税もガソリン税減税も再エネ賦課金廃止もその原資は確保できているし実行可能な 状況にある。財源に困れば「日銀保有国債の一部永久国債化」等の代替策を検討すればよ い。 国民民主党には労組を母体としない議員が少数ではあるがいる。その筆頭である玉木雄 一郎が率いるからこそ、ハイブリッドな政策を打ち出し、それを正論化するにまで昇華で きたのだろう。必ずや政策を実現し高まった国民の期待に応えて欲しい。(世良 直)
2024.11.02
~IDAとは一線を画す中国の発展途上国に対する融資の全体像~ 国際開発協会(以下、IDAという)関連法の改正法成立している。IDAとは世界銀行の関連団体である。主に低所得国向けに超長期で低利融資、もしくはグラントを提供している機関だ。同様の役割を持つ機関に国際復興開発銀行(IBRD)というものがあるが、そちらは中所得国を対象として長期融資を提供している。戦後の日本政府も新幹線網や高速道路網の整備の為にIBRDの融資を受けたことがある。それらの社会インフラ整備が進むことによって日本経済は高度経済成長を遂げたのだ。目覚ましい経済発展を遂げた日本は巨額の借入国から今では世界有数の資金供与国となっている。IDAは第二世銀と言われ、IBRDでは与信が付かないような貧困国をはじめとした発展途上国の社会資本への長期融資を行っている。 IDAに関する改正案は、IDAの増資計画に対して日本政府が約4206億円の追加出資を行うことを規定する法案だ。IDAは1960年に設立されて以来、3年ごとに増資を繰り返しており、今回は第20次の増資となる。前回の増資から2年しか経過していないが、新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックにより、ワクチンや医療提供体制を含む対応の支援の為のIDAの資金不足が見込まれた為に1年前倒して増資を行うことになったようだ。 日本は世界2位の出資国として枠組みを主導 今回の増資の計画とその枠組みの組成は日本が主導して行っている。昨年12月に日本が主催した最終会合でコロナ対策の支援規模を930億ドルとし、資金提供国から235億ドルを調達することで合意した。日本政府の負担額はこれまでの日本政府の出資比率を維持することを前提としており、3767億円を提供するとともに、最貧国の重債務に対する救援費用として438億円を追加で提供し、合計4206億円を予定している。 IDAの融資対象国は74ヶ国に上っている。通常の融資条件は40年返済、当初10年は元金を据え置き、金利は0.45%程度であるケースが多い。これに加えて融資残高の年0.75%の手数料が必要となる。 IDAの第20次の増資における日本の出資比率はこれまでと同水準を維持する方針だ。第19次の増資時の主要国の負担比率はというと、筆頭は英国で12%、続いて日本が10%、そして、アメリカが9.31%、ドイツが5.62%、フランスが5.06%、中国が3.72%、カナダが3.45%、スウェーデンが3.02%、オランダが2.93%などとなっている。名目GDPを参考にした出資比率からするとアメリカが少ないような気がする。逆にイギリスはGDP比で言うと圧倒的に大きな負担をしている。日本は2番目の負担比率であり妥当と言える。問題は中国だ。日本の約3倍のGDPを誇る中国がなんと日本の負担の1/2.5です。際立って少ない負担である。本来ならばアメリカ、中国、日本が主導して出資するのが適当であろうが、そのバランスは保たれていない。ではなぜ中国の出資は少ないのか。中国はIDAとは別に、独自の低所得国向けの融資を行っているからだ。 2020年において全世界的に深刻化するコロナ禍の中で、IMFと世界銀行は融資している73ヶ国を対象として返済支払猶予をG20に対して要請している。低所得国が十分なコロナ対策をとる為の人道上の理由と共に世界経済の回復を促進するための施策だ。この73ヶ国はIDAの融資先国とほぼ同一である。それに対してG20の一員である中国も他国と足並みを揃えて支払猶予を受け入れている。中国は拒否することもできたが、中国によって債務危機に陥ったと各国に指摘されることを避けたのだろう。このことは、IDAが中国無しでは債務危機に対応できないということを明らかにすることとなった。 中国の低所得国向け融資─G7の2倍 中国が独自に行っている低所得国への融資の残高は1030億ドルに達している。一方、世界銀行(IBRD、IDAを含む)の低所得国への融資残高は1157億ドルである。そのうち、G7の融資残高は571億ドル、中でも日本の融資残高が239億ドルなので、中国が1国でいかに巨額の融資を低所得国へ行っているかがわかる。中国の融資規模はG7と比べて約2倍、日本と比べて4.5倍に上っている。 中国はなぜ独自路線をとるのか。それは、単独での融資は中国に都合の良い発展途上国を恣意的に選別して融資できるからだ。 中国からの融資が大きい国はパキスタンとアンゴラである。パキスタンは215億ドル、アンゴラは157億ドルだ。中国から100億ドルを超える融資を受けているのはこの2カ国だけである。パキスタンとアンゴラが重視されるのは、両国が一帯一路および資源確保において欠かせない拠点になっているからだ。パキスタンはインド洋から陸路による中国への輸送を可能とする経済回廊の要である。アンゴラはナイジェリアに次ぐ産油国で、中国にとってはサウジアラビア、ロシア、イラクに次ぐ原油輸入先となっている。 中国の融資スタンスは独自の経済的な権益の確保にあるので世界銀行に比べて与信が緩い傾向にある。中国の融資先には返済負担率が非常に高い国が多くみられる。ジプチの負担率は37%、コンゴは29%、ラオスは27%、キルギスは21%、モルディブは20%となっている。世界銀行の融資先ではカーボンベルデが20%を超えているが、その他には負担率が20%を超えている国はない。 中国に依存している国は、一帯一路(キルギス、ジブチ)、南シナ海における領有権確保(ラオス、カンボジア)、資源確保(コンゴ共和国)、インド洋、太平洋への進出(モルディブ、トンガ)といった外交戦略において重視されている国々である。これら中国依存国のリスクが「高い」、乃至は「窮迫」と評価されるのは、債務の持続可能性よりも外交上の利益を優先する中国と新たな債権国として存在感を高めている中国を積極的に利用しようとする低所得国の思惑が一致したからである。 中国はG7各国を含め世界的に疑心暗鬼を招いてきた。返済負担率を無視した低所得国への融資を自国の利害の為に行って来たからだ。中国は融資によって世界各国に影響力を強めてアメリカに対抗する勢力圏の構築を目論んでいるとされている。だが、中国が強権的に融資先国を従えるような振る舞いは意外にも見られない。中国に依存する国も利害関係が一致することからこそ依存しているのである。それぞれの国が主体的に国家運営を行っているのは間違いない。 中国は自国の飛躍的経済発展による資金力を背景に一帯一路をおし進めてきたわけだが、今後もその路線で行くのかというとそう容易いことではないようだ。他国への融資によって急激な資金力の低下を招いていることと中国国内でのインフラ投資が一巡し、且つ米国をはじめとした先進国との貿易摩擦が拡大していることから国内の景気は失速しがちな状況となっている。 中国は決して発展途上国の盟主ではないのかもしれない。中国は自らを「開発途上国」とする一方で、欧米諸国を源流とする価値観や制度を代替しうる「大国」としてきた。つまり、国際社会における立ち位置を都合よく使い分けてきた。中国は、「中国モデル」を欧米諸国に追従しない経済発展の道としながらも、それが具体的にどのようなものであるのかについては必ずしも明らかにして来なかった。中国は確かに長期にわたり安定的な成長を続けて来たが、政治、経済、社会などの初期条件が異なる国に、その経験をどのように移植すれば成功するかということは何も示していない。そればかりか、中国は深刻化するアメリカとの対立、潜在成長率の低下、そして、最近の債務危機においても開発途上国を満足させる対応が出来ていない。中国の求心力が低下するのは当然とことと言える。 他方、米国のバイデン大統領は同盟国との同盟強化を急いでいる。中国は経済回復のペースが速く、G20のなかで唯一プラス成長が期待出来る国だ。中国は発展途上国への積極的な融資を再開する体制が整いつつある。ただし、新型コロナウイルスの蔓延による途上国の経済状況の悪化がそれを阻んでいる。 日本はこれまでの路線を堅持し、世界銀行及びIDAにも積極的に関与を強め、中国の権威的かつ高圧的な外交姿勢に対して頂門の一針となるよう期さなければならないのではないか。